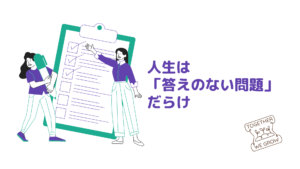ネブタとか、ねぶたとか、立佞武多とか【2025】

こんにちは!茉莉(まつり)デザインです。
屋号のとおり、祭りが好きな私です。
今回は、今年の祭りを見に行って思ったことを、つらつらと書いていきます。
特に役立つような情報はなく、祭り好きの雑記ですのでご了承ください。
7/27 つがる市ネブタ祭り
今年の青森県内の夏祭りでは、1番最初らしい。(毎年なのかな?)
今年五所川原に引っ越してきた私は、
パートナー(モフさん)と一緒に隣の市へ見に行ってみることに。
フジロックの中継をやってたので、Creepy Nutsのステージを聴きながら田んぼの中を車で駆け抜ける。
フジロック以上に自然を感じてるんじゃないか!?と錯覚しながら、つがる市へ向かう。
つがる市のねぶたは初めて見る。
ちなみに正式な名称はネブタとカタカナらしい。
青森県内の祭りの表記はほんと複雑だ。笑
ねぶた前、道路に出て体を動かす子どもたち。

わかるよその気持ち、夏がキタキタ〜って感じだよね。
私も飛び出したい。けど33歳だから我慢する。
五所の立佞武多に近いのかと思ってたけど、山車は横型のねぶた。
↑ちょっと竹浪さんのねぶたっぽい面。
囃子も青森ねぶたに近いかな?ころばしっぽい。
実際に青森のねぶた囃子をやってる団体もあった。
かと思えば五所の囃子をやってたり、弘前のねぷた絵っぽい山車もある。
いろんな文化が交差していて、たのしい。

ちいかわもいる。

つがる市の祭りのルートは短い。
もっと長くてもいいのにね。
8/2 青森ねぶた祭
モフさんと見に行く。
早く着いたので、UNDER LOUNGEで待機。
ここはガラス張りで外が見れるのでうれしい。
参加する人も、見る人も、ねぶたとかどうでもいいから交通規制前に早く帰りたいわ〜って人も、
とにかくみんなソワソワしている。

ノンアルモヒートをズビズビすすっていると、市民ねぶたがやってきた。
灯がつく前のねぶた。
灯がついたらどうなのか、ワクワクする時間が好きだ。
期待どおりなのか、期待を超えてくるのか。
今年は麻子さんのねぶたの雲の色がグラデーションがかっていて、これがどうなるのか気になっていた。

市役所の配電盤前で待機。
ワタワタとボランティアの子達が有料席のパイプ椅子を並べていくのを眺める。
いつから有料席って車道になったんだっけ?と浦島太郎のような気持ちでぼんやりする。

7時になると遠くで囃子が聞こえ始めて、ちょっと待っていると奥からぬらぬらと大集団がやってくる。
かっこいい。
やっぱねぶただよな。
今年はNebuta Life用の撮影を頼まれていて、慌ただしくカメラを回しながらも、先頭の麻子さんのねぶたを見る。
おぉ〜こんな風に見えるんだ!とうれしくなる。
すぐ行ってしまう。
ねぶたが見れるのは意外と一瞬だ。
でもその儚さがいい。
どのねぶたも素晴らしいが、私は特にパナソニックの蓮明さんのねぶたに感動した。
蓮明さんは今年から息子の春一さんに1台譲った。
でもこのパナの1台に2台分、というかそれ以上のパワーを漲らせている。
力強さの中に可憐なお花も散りばめられたりしちゃって、細けぇ…。
本当にこの人はねぶたに命懸けてるんだなぁという魂を感じて、涙が出そうになる。
一方、モフさんは「他は龍とか鬼とかばっかりだから、独創性があっていい」と、市P連の送りのナマズをいたく気に入っていた。


人それぞれの楽しみ方があるから、ねぶたはおもしろい。
8/3 五所川原花火大会
五所の花火も今年初めて。
この世の中にはまだ経験してないことがたくさんあるなぁとつくづく思う。
いつも青森の花火は少し離れたところから見てるというのもあるかもしれないが、五所の花火はすごかった。
あとたぶん気合い入りすぎてるだと思うけど、当日の開始前、30分おきに花火が鳴っていた。
これはそんなに鳴らさなくてもいいのになと思った。笑
パンフレットを開くと、たくさんの五所川原(+近隣市町村)の企業の名前が載っている。
1つの演目で何百万円もするだろうにすごいなぁ、私もこうやって還元できるようにならなきゃなぁ、と謎の使命感を抱く。
こちらは、なんとなくディズニーランドみのあるオープニング。
8/4 五所川原立佞武多
今日から立佞武多が始まる。
モフさんと椅子を持っていってつがる総合の方で見ることにした。
明るい囃子が聞こえてくる。
五所の囃子はお尻をフリフリしたり、鉦をダイナミックに回したりと、テンションが高くて好きだ。
先陣を切って現れたのは知事。
知事が現れるとテンションがあがるのは青森だけなのだろうか。
五所川原は縦長の立佞武多もあるのだけど、横長のねぶたもあって、バラエティ豊かで楽しい。
踊り子みたいなみなさんがいるのも、青森と違うところだ。
高校でも出陣している。
ちょっとシャイな感じの子もいれば、イキイキしている子もいて、思春期の縮図だなぁと思いながら眺める。
誠和會というところは正調囃子をやっているということも今年わかったので、聴き比べたりして楽しむ。
ちなみに今年の最高賞・五所川原市長賞はこちらの「不動明王」でした。
「暫」は今年で見納めだったような?
まだ五所川原のことはあまりわからない。
8/5 青森ねぶた祭
本番前、1人で鬼平に寄る。
行ったらちょうど、この日の予約の人数を間違えていたらしく、てんやわんやしている。
夏だな、と思いながら私は冷たいそば茶をいただく。
ごたごたも落ち着いて、鬼平の女将・まちこさんと雑談。

吹き流し方式よりも一斉スタートの方がいいよね、という話になる。
私もそう思う。
本町側に最初から活気を与えてあげてほしい。
吹き流しのままなら、ホテル青森の方にもスタート地点を増やしてもいいんじゃないだろうか。
鬼平横でまやちゃんが売ってるヤバインミーを買う。
ラジオの仕事もデザインもバーテンもやってて、バイタリティすごい。笑

この日一緒に撮影するかくまさんの分も買って、合流して食べる。うまー!
協同の近くの場所をかくまさんが確保してくれていた。椅子持参で。やさしい。
かくまさんは長野県松本市の出身だが、地域おこし協力隊として青森市に住んで約3年になるらしい。
「地元にはこんな規模の大きい祭りはないから、おもしろいです!」と言ってくれる。
自分の地元を他県の人が気に入ってくれると、こんなに誇らしいことはない。
立佞武多については「まだ勉強不足で、忠汰さんという制作者の方しかわからないです〜」と話していたが、私より十分詳しい。
撮影中に青森山田学園のねぶたが来た時も、「ねぶたに出れば単位もらえる授業があるらしいですよね〜」とねぶた小話まで披露してくれる。
1つの団体の囃子方っていう狭いところに20余年いた私よりも、うんと広い視野で祭りを見て楽しんでるな〜と感心する。
撮影が終わり、帰路につきつつ本町の方へ行く。
本町は道が狭くなるせいか、みんなの熱気があがる感じがして好きだ。
東北電力のねぶたが信号機に引っかかってなかなか脱出できないでいた。
左右前後に動かしてみるがどうにも動かない。
結局エイヤっと出てきたが、鬼の右手がズル剥けてしまった。
明日立田先生が一生懸命直すんだろな〜と、灼熱のねぶた小屋のことを考える。
酒に酔って大男に喧嘩を売っている子連れの女性や、道でゲロを吐く女の子を横目に駐車場へ向かう。
夏のせいだよね。
8/6 五所川原立佞武多
今日は立佞武多見に行くよ、とモフさんに伝えたら、ビョーキなんじゃないかと心配される。
そうだよ、ほとんどビョーキなんだよ。笑
でも明日は大雨予報だし、あさっては仕事だし、あと見るなら今日しかないんだよ!と1人で見に行く。
立佞武多の館から出陣するところを見てみたかったので、館の近くに行ってみる。
この日も雨の予報が出ていたせいかお客さんが少なく、しれっと3列目ぐらいに加わることができた。
ちなみに、今年は立佞武多の館が休館していて、大型立佞武多の新作がない。
それもあってお客さんが少ないのだろう。
残念すぎると思っていたが中型の新作「織姫と彦星」の制作はあった、ということに気がついたのは祭りが終わってからだった…。
はじめて館のあたりで見たけど、集合地点にいっぱい集まる青森ねぶたと違ってぬるっと出てくるからおもしろい。
津軽弁で「べろっと」という擬態語が1番好きなのだが、立佞武多はべろっと出てくる、という表現が似合う気がする。
他の団体を見ていて「おぉ〜かっこいいな。綺麗だな。」と送り絵まで見ているうちに、ハッと振り向くとそこに23メートルの山車がべろっと現れる。
観光客のおばちゃんと共に、毎度立佞武多の出現にびっくりしながら、堪能する。


立佞武多は1周1時間ぐらいで、最後の山車を見送ると、数分後には先頭の山車の顔が見え始める。
巨体の頭がビルの上から見えるので、場所がわかりやすくていい。
少し場所を変えて、今度は戻り囃子(たぶん)を聞く。
祭りが終わりに向かっていく。
8/7 五所川原立佞武多
7日も立佞武多を見にいきたかったけど、仕事で間に合わず、津軽道から眺めただけでぬるっと終わってしまった。
家についたらぬるぬるした奴が玄関で出迎えてくれた…。
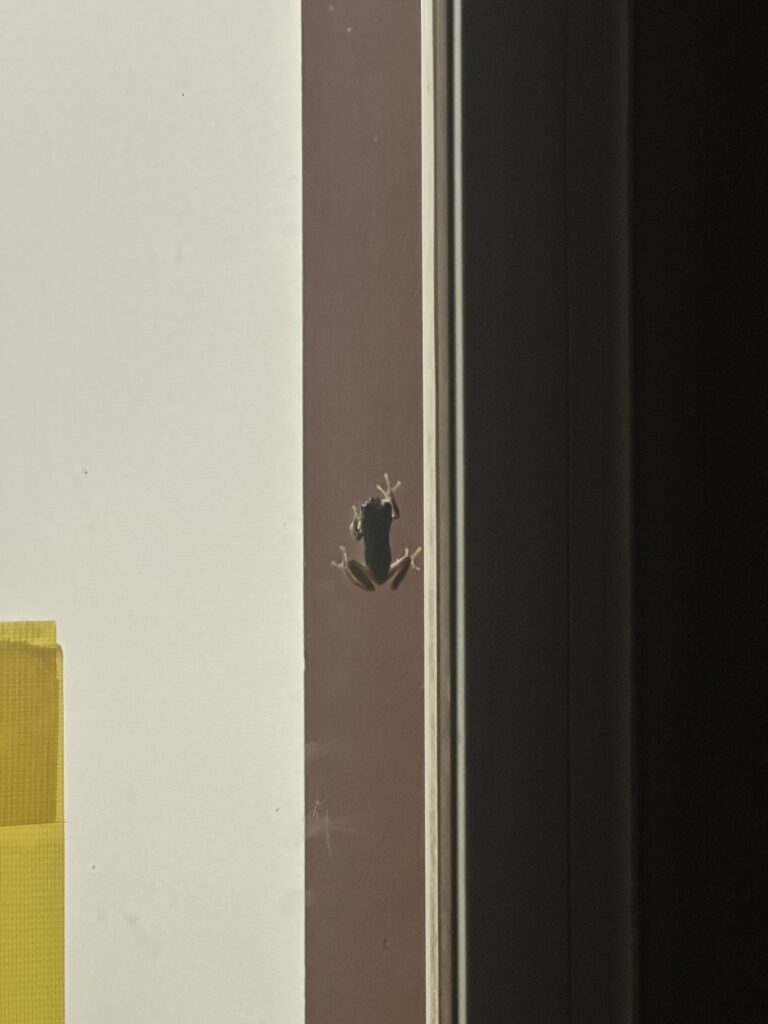
おわりに
以上、2025年の青森の祭り、たくさん楽しんで過ごしました!
と言っても弘前に行けなかったけども…何年も見に行ってないな〜。
あと荒馬まつりとかも見てみたいです。
つがる市は馬市まつりもあるので、来年こそ見るぞ🐴
(今年は予定が合わなくて行けない🥲)
人からも祭りからもパワーを吸収したので、
また秋から1年仕事をがんばりたいと思います💪笑
ご意見・ご相談はこちらから